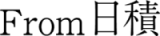万葉集「大畠の鳴門」

大島の鳴門 「万葉の歌10 中国・四国」 p160
玉藻刈る娘子
遣新羅使人のひとり、田辺秋庭は大島の鳴門で、渦潮につかりながら美しい藻を刈る海人おとめたちを見て歓声をあげた。それが歌となって残された。
大島の鳴門を過ぎて再宿を経ぬる後に、追ひて作る歌二首
これやこの 名に負ふ鳴門の 渦潮に 玉藻刈るとふ 海女娘子ども(卷15-3638)
上の一首 田辺秋庭
波の上に 浮き寝せし夕 あど思へか 心悲しく 夢に見えつる (卷15-3639)
「大島の鳴門を過ぎて…」と題詞にある大島は、筑紫路の 可太の大島 しましくも 見ねば恋しき 妹を置きて来ぬ (卷15-3634)
とも歌われていて、「可太の大島」ともいわれている。「可太」は、『万葉代匠記』に「筑紫路の方の大島」の意か、それとも「可太の大島」という地名かといい、井上『新考』には「案ずるに可太は方なり。…大島は諸国にある名なれば取分きて筑紫路の方の大島といへるなり」とする。鴻巣『全釈』は、「可太はこの附近の古名らしい」とするがこれも根拠にとぼしい。なぜ「可太」の大島といったのか不明である。
『古事記』の伊邪那岐、伊邪那美二神の国生み神話で、大八島国を生んだのち、吉備児島、小豆島、つぎに大島を生んだと記される。『和名抄』には「周防国大島郡」とあり、屋代、美敷、務理の三郷がみえ、いまの周防大島がひとつの郡となっていたことがわかる。大島は一名、屋代島ともいって、いまは四つの町からなっている。山陽本線大畠駅の南東に浮かぶ大きな島であり、神話の昔から名が知られていた。大島はいまではみかんの産地として知られ、総面積180平方キロ、山々の斜面にはみかん畑が広がる。昭和51年(1976)7月大島大橋が完成した。JR大畠駅のすぐ東から大島町小松へ、大畠瀬戸をひと跨ぎにする。大島大橋は全長1020メートルである。この海峡が万葉の「大島の鳴門」である。
海の難所
頭書の二首は、「大島の鳴門を過ぎて再宿を経ぬる後」に作ったとある。このことは、この海峡が万葉びとにとっていかに難所であったかを物語っている。彼らはいままでもいくつかの難所を通ってきた。「物に属けて思ひを発す歌」という長歌に、
……沖辺には、白波高み 浦廻より 漕ぎて渡れば 我妹子に 淡路の島は 夕されば 雲居隠りぬ さ夜ふけて 行くへを知らに 我が心 明石の浦に 舟泊めて 浮き寝をしつつ…
とある。彼らにとって第一の難関は明石海峡であった。沖の高い波を避け、浦伝いに漕ぎ進み、明石の浦に碇泊したという。幅4キロ足らずのこの海峡は、第五管区海上保安本部調べによると、潮流の最高速度が西流7.1ノット(時速13キロ)、東流5.6ノット(時速10.4キロ)と観測されている。明石の浦は明石川が海峡に流れ込む河口あたりであったろう。一行の船はここに船舶まりしたようだが、ここは潮流が最も速いといわれる舞子沖から5.6キロ西寄りになる。万葉のころもそうだったとすれば、海峡の激しい流れにのって必死の思いで、やっと明石の浦に船を漕ぎ入れたのであろう。
大畠の瀬戸の潮流は時速3キロであるが、明石海峡のように幅は広くない。狭いところで1キロあまりであるから、それだけに危険も伴ったろう。ここを乗り切るまでは歌を作る余裕などなかったものとみえる。さきの明石の浦を詠みこんだ長歌も、結びのところに玉の浦に碇泊したときの心境を述べているから、明石の浦では作歌する心の余裕はなかったとみてよい。ところどころで、古歌を誦咏することはあった。明石海峡では人麻呂の歌「天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ」を思い浮かべ、第五句を「家のあたり見ゆ」と誦咏している。この歌とて、明石の浦に碇泊してほっとしたところで詠じたに相違ない。難所の通過は船に乗っている全員にとって命がけのときだった。
渦潮と娘子
大島大橋の上から眺めると、いまも急潮のつくる渦は壮観である。「これやこの名に負ふ鳴門の」との感はいまも変わらない。ただ、玉藻刈る海人おとめの姿はない。都ではここを旅した経験者の間で高い噂になっていたのだ。これがあの名高い、大島の鳴門で渦潮につかって藻を刈る海人おとめなんだなあ。期待していたものに出会ったときの驚きと喜びが、歌全体にみなぎっている。
この海峡は、潮が満ちてくるときは激しく東流し、引くときは激しく西流する。潮流が停止するのは、わずか三、四十分ほどだ。しかし、海人おとめたちはその時を待たず、激しい潮流に足をとられないように、たくましく藻を刈っているのだ。都びとたちが目を見はったのは、その苛酷とも思われる労働を事もなげにやり抜いている海人おとめたちへの驚嘆と賛嘆であった。あるいは、そういう乙女に対する憧憬であったかも知れない。
歌の作者たち
この歌の作者、田辺秋庭がどういう人か不明である。ただ、大使、副使、大判官、少判官など上位の者は官職名で記されているから、秋庭は下位の随員の一人であったのだろう。
「波の上に浮き寝せし夕……」の歌と、「筑紫道の可太の大島……」の歌には作者名がない。それぞれ都に置いてきた愛妻を思う歌だ。前者は、船の上での浮き寝に妻の夢を見た。妻が自分のことを思ってくれている証拠だと思えば、会いたさから悲しくなってしまうのだ。後者は、はじめ二句は、シマの音のくり返しによって次の「しましく」を導き出す序詞である。都を出てからもう半月は経っていたろう。ちょっとの間でも会えないと恋しくてたまらないのに、もう何年も会ってない気がして、いたたまれない気持ちになっているのだ。こうした彼らの歌をみると、時折、はじめて見る景観に好奇の目を輝かし、驚きの声をあげてはいるが、歌々を一貫しているのは、郷愁と妻恋のほかの何者でもない。これは、朝命を帯びての旅とはいえ、素直に正直に自らの心をみつめれば、任務よりも、一個の人間としての心情をおさえ切れなかったことを物語っている。それでこそ人間なのだろう。赤裸々な真情に親しみをさえ感じる。そんな万葉びとの心がなぜかわれわれに、安らぎを与えてくれる。人間らしさがわれわれの魂を救ってくれるというほうが当たっていようか。
渦潮の瀬戸
大畠駅から五分ほど歩けば、大島大橋の袂に着く。橋の歩道を大島に向けて歩めば、バスやトラック、乗用車などがひっきりなしに、轟音を響かせて通りすぎる。鋼材とコンクリートで構築された橋も不気味に揺れる。橋の上から渦潮が見える。いくつも輪を描いて渦巻いては拡がり、その渦があるいは並びあるいは重なりして、潮流の複雑さを目のあたりに見ることができる。当時、外洋を渡る大型船で、全長がせいぜい二、三十メートル、幅七、八メートルというから、この大島の鳴門の渦潮を乗りきるにも、われわれの想像を絶する不安があったと推測できる。それにこの辺の海底には暗礁が多く、有能な水先案内がいないと危険がいっぱいの海峡といわれる。いまでも、渦潮を乗り越えて行く機帆船は、直進できず蛇行運転するほどである。
大橋を渡って左手に、瀬戸公園がある。斜面を少し登ったところに、田辺秋庭の歌の碑が立っている。昭和51年(1976)7月大島大橋開通を記念して建てられた。武田祐吉氏の揮毫で鮮やかに刻まれている。
○[万葉の歌10中国・四国]p165[熊毛の浦]熊毛の浦は、山口県熊毛郡上関町の室津説、熊毛郡平生町の小郡から尾国にかけての入海説、光市室積説などがある。熊毛の浦に舟泊まりする夜に作る歌4首。○[都返(みやこへ)に/行かむ舟もが/刈り薦の/乱れて思ふ/こと告げ遣(や)らむ](巻15-3640)右の一首羽栗。○[暁(あかつき)の/家恋(いえごい)しきに/浦廻(うらみ)より/梶(かじ)の音するは/海人娘子(あまおとめ)かも](巻15-3641)○[沖辺(おきへ)より/潮満ち来らし/可良(から)の浦に/あさりする鶴/鳴きて騒きぬ](巻15-3642)○[沖辺より/舟人上る/呼び寄せて/いざ告げ遣らむ/旅の宿(やど)りを](巻15-3643)一首目の作者、羽栗は名を記していないので、羽栗吉麻呂かその子の翼・翔、三人のうちの誰かわからない。父吉麻呂は霊亀二年(716)安倍仲麻呂の従者として唐へ渡り、彼の国で妻をめとって翼、翔の兄弟をもうけ、天平6年(734)二児を連れて帰国した。翼はその時16歳であった。このたびの遣新羅使派遣は天平8年(736)であるから、翼は18歳で、しかも帰朝して2年しか経っていないことから、この歌の作者と考えることに少し無理があるようだ。弟の翔にいたってはなおさらのことであろう。とすれば父の吉麻呂かというに決定する根拠はない。ただ歌を読み味わうと都に妻を残している趣があり、やはり吉麻呂であったのだろうか。
○[万葉の歌]①p167[可良(から)の浦]→可良の浦はどこか。おもだか[注釈]に、室津半島の熊毛郡平生町の小郡から尾国にわたる海岸、つまり熊毛の浦の一部を可良の浦ともいったとみているのに従っておきたい。武田[全注釈]が所在不明としながら、[くまげの浦の付近であろう。沖の方から潮が満ちて来るというによれば、深い湾内である]といっているのは、いま、室津半島の西海岸、小郡から尾国にかけて深く湾入した地形から、そのあたりを指しているのだろう。[・・可良の浦にあさりする鶴鳴きて騒きぬ]とあって鶴が群れて餌をあさっている状況から、近くに鶴の棲息に適した湿原や沼地があったにちがいない。
いま、JR柳井駅からバスで南下すること約一時間、室津半島の南端室津に着く。その道中、西方海上に展開する多島美は目を見はるばかりの奇観絶景である。馬島、牛島、佐合島、祝島、小祝島、長島と、遠く近く大小さまざまな島また島、すばらしい景観である。小郡から尾国にかけて海は深く湾入していて、いまでは護岸のコンクリート壁に囲われているが、壁の外側は白砂の渚に清澄(せいりょう)な波が静かに寄せている。西と南は長島が周防灘の風波をさえぎり、東は北の大星山(438m)から南の皇座山(527m)にかけて尾根つづきで、東風もほぼ完全に遮断される。だから、この深い湾内はじつに穏やかで鏡のような静けさである。ここを可良の海と考えるに、いささかの疑問もない。平生町尾国八幡宮の篤学の人・大本信雄氏によれば、この小郡から尾国付近の地名にカラのつくものがあるという。尾国南方の岬を唐釜(韓竈)とも。現在カリカマと訛っていったりする。往古はいまの上関をカマ(ド)の関といい、室津と上関付近の海をカマ(竈)の浦といった。そのカマの浦とカラの浦と両方を見渡せる所という意味からカラカマと呼ばれたのだろうという)、また、小郡から東方の阿月に越える峠道を唐門(韓門)[カランドウ]とも。
これは現在カナンドウと訛っていったりする)などと呼ぶ。これらは、いまの小郡から尾国にかけての深い湾内を[可良の海]といっていたことの手がかりになり得よう。
○[②]むら岡良弼の[日本地理志科]に[万葉集ニ熊毛ノ浦有リ、一名可良泊、可良ハ韓ナリ、韓人入貢シ此ニ繋泊ス、因テ名ズク]とあるように、熊毛の浦は一名可良泊(からどまり)とも呼ばれたのであろう。