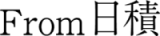天然痘

○730年1月13日筑前。大宰府で梅花の宴。旅人、憶良らが歌で心をいやす。
○【天然痘大流行、藤原兄弟あいついで死去】737年(奈良)4月17日に参議民部卿の藤原房前【フササキ】(57)が死去したが、6月から8月にかけて参議兵部卿の藤原麻呂(43)、左大臣の藤原武智麻呂(58)、参議式部卿兼大宰帥の藤原宇合【ウマカイ】(44)、中納言多治比県守(70)らの政治高官が、あいついで死亡した。原因は735年夏から冬にかけて大宰府管内から流行した天然痘によるものと思われる。すでに同じ病で新田部親王、知太宰府舎人親王らを失っている太政官にとっては大打撃である。特に4兄弟が協力して政権の中枢を握っていた藤原氏にとっては、一挙に4兄弟を失った打撃は大きく、今後の政局への影響ははかりしれないものがある。典薬寮(てんやくりょう)の発表によれば、天然痘にかかると5、6日で発疹がみられ、3、4日は高熱を発し水を飲みたがる。その後発疹と熱はひくが、かわって下痢をし、手遅れになると血便がみられ死亡するという。天然痘は、734年暮れに大宰府に着いた新羅使、翌年3月に帰国した遣唐使、この年正月に新羅から帰国した遣新羅使らによって海外からもたらされたと推測されている。735年に流行した天然痘は翌年いったん下火になったが、この年4月にふたたび大宰府で発生、たちまち広まった。政府は全国各地にふたたび救済の手をさしのべてはいるが、その効果ははかばかしくなく、多数の農民が死亡し農業生産は低下している。典薬寮は治療法として腹腰を布や綿で温め、寝床にすの子やむしろを敷いて寝かせ、海藻や塩を口に含んでいること、洗浴、房事、風雨にあたることを禁ずることなどを諸国司に通達し、その沈静化に躍起でる。
【日本全史】ジャパンクロニックより。
○大仏造立、国民に呼びかけ
聖武天皇が安寧を願って造立した大仏。マスクをつけた参拝者が次々と訪れる。淡い光が差し込む堂内に読経が響き渡る。奈良市の東大寺大仏殿。高さ約15メートルの盧舎那仏坐像るしゃなぶつざぞう(大仏)の前でマスク姿の僧侶が祈りをささげる。コロナ禍の早期収束を願う勤行だ。その場にいた参拝者も静かに目を閉じる。
「世の安寧のために祈る。これはずっと続けてきたことです」と森本公穣・庶務執事は語る。つまり、大仏が造立された奈良時代から受け継がれてきた営みである。
当時、日本国内は疫病によって未曽有の混乱に陥っていた。海の向こうとの交流が盛んになり、グローバル化が進んだ時代。大陸から九州へ持ち込まれた天然痘が735年、各地へ広がった。737年も再び流行し、死者が続出する。政権の中枢を担った藤原4兄弟を含む多くの貴族たちも命を落とした。
史書・続日本紀(しょくにほんぎ)によると、聖武天皇は「私の不徳によってこの災厄を生じた」と自らを責めた。税の減免、米の支給、資金の貸し付け……。現代にも通じる応急対策を打ち出し、疫病の症状などを記した文書を諸国に示した。
さらに国家の命運をかけて発したのが、743年の「大仏造立の詔(みことのり)」である。仏教の力によって困難を克服し、平穏な社会を取り戻そうという巨大事業。完成までに10年近くを費やした。
奈良時代、国内に広がった天然痘はどれほどの被害をもたらしたのか。
「死者は人口の25~35%に上っていただろう」
日本史を研究する米国人のウィリアム・ファリス・米ハワイ大名誉教授(歴史人口学)は1985年発表の論文でそんな推計を明らかにした。
当時の人口は450万人程度とされ、実に100万~150万人が死亡したことになる。ファリスさんは「増え続けていた人口が一気にしぼんだ。壊滅的だったといえるのでは」と指摘する。
出展される「長門国正税帳(ながとのくにしょうぜいちょう)」。中央に「疫病」の文字がある
奈良時代に政治の中心だった平城宮跡の大極殿(復元)。都でも多くの人が犠牲になった。推計の根拠となったのは、正倉院宝物として伝わる古文書・正税帳しょうぜいちょうの記述だ。
律令制のもと、中央政府が地方財政を把握するため諸国に毎年提出させた帳簿で、今も20件余りが残る。うち「長門国(ながとのくに)正税帳」など5件は天然痘が大流行した737年の文書。耕作放棄が増え、「備蓄米を増やせない」などと疫病の影響に触れる。
ファリスさんは、困窮農民に貸し付けられていた稲束の数と、農民の死亡で返済が免除された稲束の数の記載に着目した。返済免除率はそのまま地域の死者の割合に近似すると考え、「死亡率25~35%」をはじき出したという。
実際この年、高位の貴族は3人に1人が死亡したとの記録がある。「かなり信頼できる数字だろう」とするのは栄原永遠男(とわお)・大阪市立大名誉教授(日本古代史)。「古代の状況を克明に伝える正倉院文書は、世界でも例のない貴重な資料だ」と話す。
疫病が社会に与える影響は大きい。奈良時代もまさにそうだった。人口の25%以上が失われた結果、深刻化したのは国土の荒廃だ。史書・続日本紀(しょくにほんぎ)は「田の苗は枯れしぼんでしまった」と記す。
そのため、疲弊する地域の復興対策として登場したのが、教科書で知られる「墾田永年私財法」である。自ら耕した農地であれば、私有化できることを認める制度だ。
律令制のもとでは、土地は国家のもので、農民が亡くなれば耕地も国家に返納された。当然、生産意欲は高まらず、疫病の流行によって田畑の荒廃はさらに進んでいた。その状況が劇的に変わった。
吉川真司・京都大教授(日本古代史)は「これで開発が一気に進み、早期に国力が回復した」と解説する。土地政策の転換は「荘園」と呼ばれる大規模農地を生み、やがて国家のかたちをも変えていく。「疫病が社会変革の大きな契機になることを歴史は物語っている」という。
新しい文化も生まれたと唱えるのは、上野誠・奈良大教授(万葉文化論)だ。万葉集の歌が変化したとみる。
〈君が行く 海辺の宿に 霧立たば 我が立ち嘆く 息と知りませ〉(あなたが行く海辺の宿に霧が立ったなら、それは、都で嘆く私の息だと思ってください)
遣新羅使しとして大陸に渡る夫を見送った妻の歌で、「永遠の別れを意識した内容。こうした緊張感に満ちた歌が増えた時代でもある」と上野さんは語る。
コロナ禍に向き合う私たちも今、歴史の転換点にいるのかもしれない。